2020/7/17
世界を描く💅老健3階
こんにちは。菜乃花リハビリテーション部門ブログ担当です。
前回の記事では、「介護サービスの種類と選び方」というタイトルで
簡単にサービスの内容をご紹介しました。
前回はこちらから
今回は介護保険でのリハビリテーションの紹介です。
― “生活のリハビリ”という考え方 ―
リハビリテーションと聞くと、「病院で行う治療」というイメージを持たれる方が多いかもしれません。
しかし、介護保険の中で行われるリハビリは、少し違った意味を持っています。
それは、病気を治すためではなく、
“生活を取り戻すため”のリハビリです。
介護保険制度の中で、リハビリはどんな役割を担っているのか――
今回は、「生活のリハビリ」という視点から、
現場での取り組みを交えてご紹介します。
1. 医療のリハビリと、介護のリハビリはどう違う?
医療保険でのリハビリは、主に「機能回復」や「治療」を目的としています。
たとえば、脳卒中後の麻痺を改善したり、骨折のあとの関節を動かしたりすること。
一方、介護保険でのリハビリは、
“生活の中でできることを増やす”ための支援です。
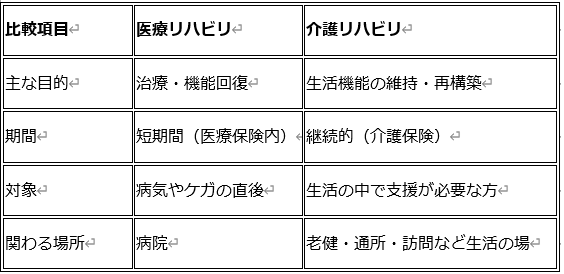
⇒つまり、介護保険のリハビリは“その人の暮らし”を治すリハビリ。
日々の生活動作(立つ・食べる・歩く・笑う)を取り戻す支援です。
2. 「生活のリハビリ」とは?
生活のリハビリとは、
動作の練習だけでなく、生活の流れ全体を整える支援です。
たとえば…
・朝、ベッドから起き上がる → 体幹バランスと覚醒を促す
・洗面台に立つ → 立位保持と上肢活動の両立
・食事をとる → 姿勢・嚥下・手の使い方の総合的な活動
・トイレへ行く → 立ち上がりと移動の再学習
どれも「生活そのものがリハビリ」になります。
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が中心となり、
「その人がどんな生活を送りたいか」に合わせて、動作・環境・意欲を総合的に支えています。
⇒生活のリハビリは、“筋肉”ではなく“人の暮らし”を鍛えるもの。

2,019年日本作業療法士会啓発ポスター
3. 継続できるリハビリ ― 介護保険の強み
医療保険では、リハビリの期間に制限があります。
しかし介護保険では、必要に応じて長期的に関わることができるのが特徴です。
・通所リハビリ(デイケア)で週1〜3回の継続訓練
・老健での在宅復帰支援と家庭への移行サポート
・訪問リハビリで在宅生活のフォロー
⇒「退院してからも支援が続く」――
これが、介護保険リハビリの最大の価値です。
継続的な関わりの中で、体調の変化や生活環境に合わせて支援を調整し、
“生活の安定と再挑戦”を繰り返し支えます。
4. 老健でのリハビリの実際
老健(介護老人保健施設)は、
医療から在宅への“中間支援施設”として、リハビリが日々行われています。
・入所時に多職種でカンファレンスを行い、在宅復帰までの目標を設定
・理学療法士は「立つ・歩く・移動する」を中心に、実際の生活動作を再学習
・作業療法士は、整容・着替え・趣味活動など「生活の質」に関わる部分を支援
・言語聴覚士は、嚥下や発声の支援を通して“食べる・話す”を支える
また、職員全員で日常生活の中にリハビリを取り入れ、
「動ける時間を生活の中に増やす」ことを重視しています。
⇒老健のリハビリは、“動作”を訓練するだけではなく、
“生活のリズムを再び整える”取り組みです。
5. 「リハビリ=専門職だけの仕事」ではない
介護保険のリハビリは、
リハビリ専門職だけでなく、チーム全体で行う取り組みです。
・介護職は、日々の生活場面での声かけや動作確認を通して支援
・看護職は、体調・服薬・栄養状態を共有し、リハビリの安全性を担保
・ケアマネジャーは、本人や家族の希望をプランに反映
・家族もまた、「一緒に支えるパートナー」として関わる
⇒老健のリハビリは、“リハ室だけ”で行うものではなく、
“生活すべてがリハビリになるようにする”ことを目指しています。
まとめ:生活を支えるリハビリという視点
介護保険の中でのリハビリは、
「治すためのリハビリ」から、「暮らすためのリハビリ」へ。
病気や障がいがあっても、
「自分の力で動ける」「自分のペースで生活できる」ことを支える――
それが、私たち老健リハビリテーション部門の役割です。
⇒“リハビリ”とは、もう一度「自分の生活を取り戻すこと」。
その小さな一歩を、チームで支え続けています。
次回予告
第4回「これからの介護保険と地域づくり」
— “支えられる側”から“支える側”へ —