2020/4/21
大人気レクリエーション🎈 老健3階
こんにちは、菜乃花リハビリテーション部門ブログ担当です。
前回は「『あぶないから動かさない』ではなく『安全に動けるようにする』」という題名で認知症の方が動くための支援の例を紹介しました。
前回はこちらから
今回は「BPSD」について少しお話します。
困っているのは誰ですか?
「困った行動」と聞くと、多くの場合、介護する側の「困りごと」が頭に浮かびます。
けれど、実は――「一番困っているのは、本人かもしれない」のです。
・なぜ今、出ていこうとしたのか?
・なぜ、怒ったような態度になったのか?
・なぜ、「そんなことしてない」と言い張るのか?
そこには、中核症状(記憶障害・判断力の低下など)に起因する“不安”や“混乱”が、背景にあることが多くあります。
「行動」は“こころのサイン”
BPSDは、医学的には「周辺症状・随伴症状」と表現されます。
これは、【脳の病変だけでなく、性格・生活歴・環境などの影響】を受けて現れる症状です。
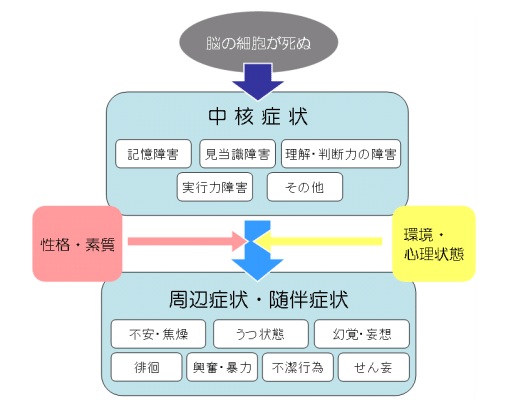
<厚生労働省HPより>
この図が示すように、行動は“中核症状 × その人らしさ × 周囲の環境”の掛け算で表れます。
つまり、本人の“こころの叫び”かもしれない行動を、「困った」と決めつけてしまうと、かえってお互いが苦しくなるのです。
例えば「徘徊」は…
「夜間の外出」「行方不明」――これはたしかにリスクが高く、“困った”行動です。
けれど本人にとっては、「家に帰らなきゃ」「子どもの迎えに行かなきゃ」など、自分なりの“理由”と“目的”があることが多いのです。
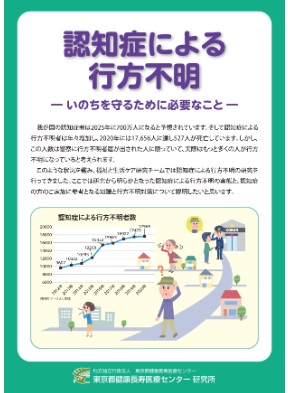
<東京都健康長寿医療センター研究所パンフレットより>
実際、行方不明となる高齢者のうち、半数以上が「認知症の可能性がある」と報告されています(※東京都健康長寿医療センターより)。
「困った人を、責めずに」「困っている人を、理解する」
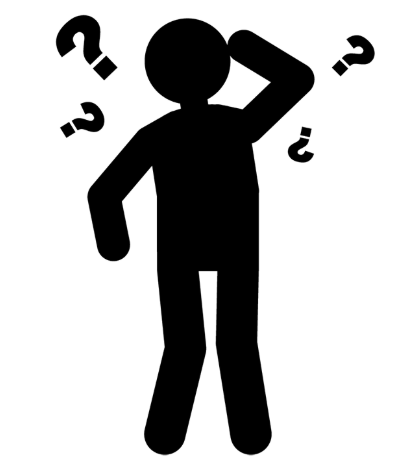
この絵のように、困っているのは――私たちの目に映っている“その行動”ではなく、心のなかの混乱や不安かもしれません。
そんな時、私たちができることは、
・「この人はなぜそうしたのか?」と想像すること
・「本人の安心」を支える環境づくり
・「自分の“困った”気持ち」も言葉にして整理すること
です。
次回は、「困った時、誰に相談すればいいの?」というお話を。
BPSDのような症状が現れたとき、ひとりで抱えこむことが一番危険です。
でも、「どこに相談すればいいのか分からない」という声も多く聞きます。
次回は、認知症にまつわる相談窓口についてお伝えします。